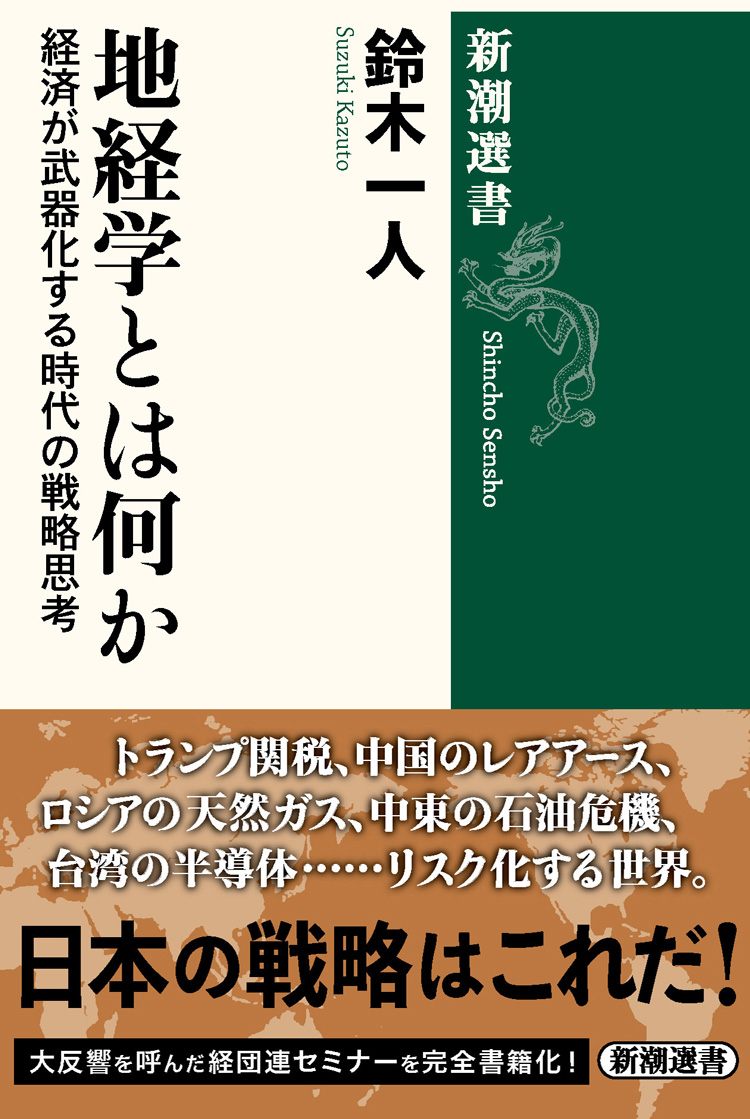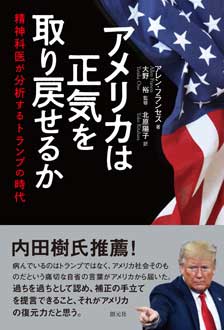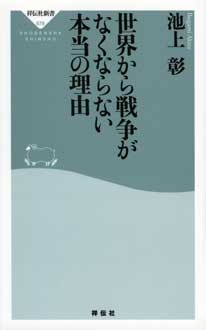2025年12月号掲載
地経学とは何か ――経済が武器化する時代の戦略思考
著者紹介
概要
今日では、他国に圧力をかける「武器」として経済が利用されるケースが増えている。トランプ関税しかり、中国のレアアース輸出規制しかり…。国際政治学の第一人者が、こうした危機の時代を乗り切る上でカギとなる視座を提示。地政学と経済安全保障を掛け合わせた「地経学」の観点から、現代の世界情勢を読み解いていく。
要約
地経学時代の経済安全保障
これまで、国家間の関係を論ずるに当たっては「地政学」という枠組みが多く用いられてきた。だが、世界が複雑化する現代、地政学だけでは国家間関係は見えてこない。これからは、「地経学」の枠組みが必要だ ―― 。
地経学とは何か
「地経学」とは、地政学と経済安全保障を組み合わせた概念である。
国家の行動や関係性は地理的な位置によって決まる、と考えるのが「地政学」である。例えば、大陸国家は国境を接する国家との力関係を重視するが、海上交通で様々な国と接する海洋国家はグローバルな力のバランスに関心を持つ。こうした形で、各国の行動が地理的に規定されていることを念頭に置きながら国際秩序を見る考え方だ。
「地経学」も、国家が地理的に規定されることを前提に置いている。ただ、地政学と異なり、その国にある経済的資源に着目して、国家が国際秩序の中でどのような役割を果たすかを考える。
例えば、ロシアがウクライナに侵攻したことで西側諸国はロシアに対して経済制裁を行ったが、多くのグローバルサウスの国々は対ロ制裁に参加することを避けた。それは、ロシアが供給するエネルギーや鉱物を得られなくなることが、彼らにとって大きなリスクになるからだ。
つまりロシアは、他国への侵略を行っても、経済的資源を持っているがゆえに、国際社会の一部からは批判を受けずにいる。このように、経済的資源を持つことで国際秩序の中で一定の力を持つというのが、地経学的パワーである。
地経学における経済安全保障
地経学における経済安全保障には、いろいろな定義がある。その中でも重要なのは、経済的手段による他国からの圧力や圧迫に対抗し得る能力を構築することである。というのも、現代の世界には様々な形で経済を「武器化」して他国に圧力をかける事例が増えているからだ。
例えば2010年、日本の尖閣諸島沖の領海に侵入した中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突するという事件が起き、海上保安庁が漁船の船長を逮捕した。中国はこの船長の解放を目的として、レアアースの日本向けの輸出を停止した。
日本は当時、レアアースの85%を中国から調達していた。このような過度な依存が、輸出停止という政治的な圧力を可能にしてしまったのだ。
経済安全保障においては、経済的な優位性を持つ国家がそれをもって他国を威圧し、その行動を抑止し、変化させようとする。従って、他国が攻撃的な手段として経済を使ってきた時に、いかに自国を守るかということが重要になるのだ。
「戦略的自律性」の考え方
経済安全保障の概念には「戦略的自律性」「戦略的不可欠性」という2つのキーワードがある。