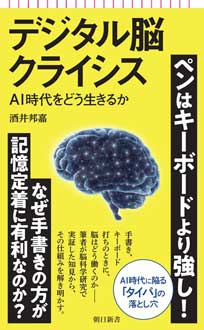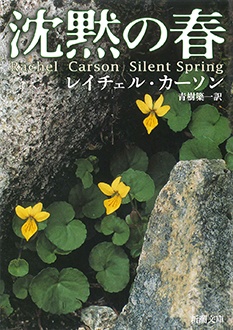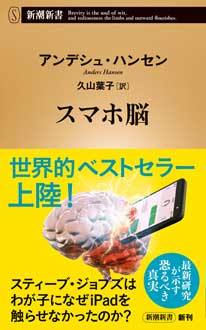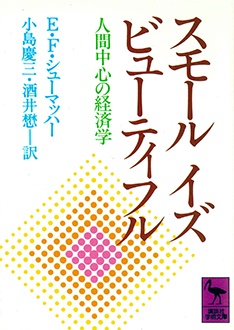2025年1月号掲載
デジタル脳クライシス AI時代をどう生きるか
- 著者
- 出版社
- 発行日2024年10月30日
- 定価990円
- ページ数237ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
スマホやタブレットなど、今や身の周りに溢れる便利なデジタル機器。だが、それに頼り過ぎると“脳”が衰えかねない ―― 。言語脳科学者が、巷に蔓延るデジタル依存、AI依存に警鐘を鳴らした。手書きとキーボードの脳への影響の違いなど、最新の研究成果を披露。紙の価値を活かし、人間の持つ創造力を伸ばすヒントを示す。
要約
デジタル機器やAIの、何が危険なのか
私たちは多くのデジタル機器に囲まれて生活している。スマホの普及はとりわけ著しく、ニュースからSNSまで片時も手放せない人は多い。
だが、生活全般でデジタル機器に依存しすぎていることに、私は強い危機感を覚える。
「もやもや感」を大切にすること
例えば、インターネット検索において、少しでも答えらしきものが得られたら、それで目的が達せられたと勘違いしてしまうという問題がある。
それは探求のゴールではなく、むしろ出発点にすぎない。書かれたことを正確に理解しようと努め、時にはその根拠を疑い、さらに自分の考えとしてまとめていく過程こそが肝要だ。
その過程は、よくわからないことがいくつもあるため、「もやもや感」を味わうことと思う。その感覚を大切にすることが、実は創造力の素養につながるのである。
イギリスの有名な詩人ジョン・キーツは、そうした「もやもや感」の大切さに気づき、「negative capability」(棚上げ能力)と呼んだ。これは、不確かなことや疑問をあえて理詰めで解決しようとはしない、むしろ問題を棚上げして、日の目を見るまで待つということだ。棚上げされた問題がある程度まで頭の中に堆積すれば、創造力の土壌になり、解決の糸口につながる可能性がある。
情報量が過多の時代では、棚上げすること自体が難しく、中途半端なことはできるだけ抹消して次の情報の渉猟に移るという傾向が高まっている。それは短期的な問題解決には役立つかもしれないが、中期的、長期的な問題に対しては無力だ。
AI時代をどう生きるか
人間の脳は、インターネット上の膨大な情報をどこまで受け付けてくれるのだろう。自分の好みに偏った情報の吸収を続ければ、知らず知らずのうちに「偏食」が目立つようになる。
自分にとって都合が良い情報に偏る傾向のことを「確証バイアス」という。自分の考えにとって確証の高い情報のみに目を向け、それを反証するような情報からは目を背け続けるわけだ。そもそも考える必要がないし、未知のことに挑む意欲も乏しくなる。その副作用として、思考力が低下したり、無気力になったりすることが予想される。
例えば厚生労働省によれば、精神障害者保健福祉手帳の保持者数は、2007年度(約44万3000人)から2022年度(約134万5000人)の15年間に3倍を超えた。現代人が精神のバランスを崩しやすいことに、インターネットを介した確証バイアスが一因となっている可能性がある。
インターネットからの過剰な情報摂取だけでも精神への深刻な影響が懸念されるところに、チャットGPTなどの「生成AI」(合成AI)が2023年頃から普及し始めた。特に日本人は新し物好きの傾向が強いためか、AIの危険も顧みずに飛びついた人たちの意見が目に付いた。