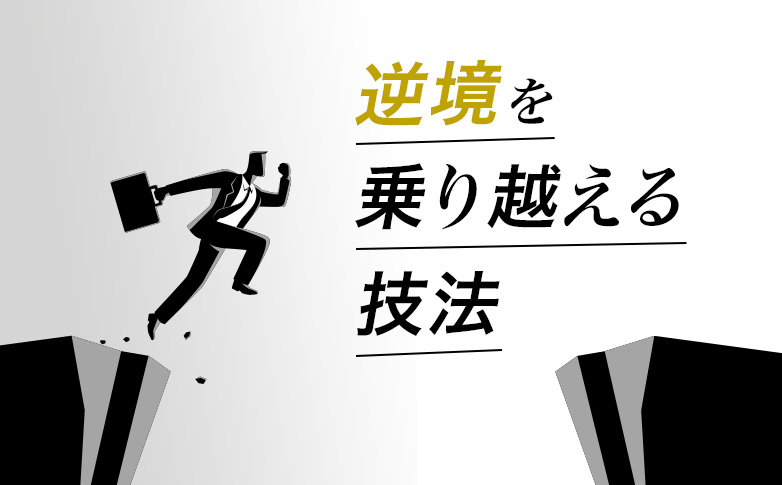1日に5500万回開催され、かかる費用は年間1兆ドル以上 ―― 。
この数字は、近年のアメリカにおける“会議”について出された試算です。
膨大なコストをかけているにもかかわらず、それに見合った成果を上げられる会議はそう多くありません。
同様のことは、日本においても言えるでしょう。
回数が多い、時間が長い、参加者が多い…。
今回は、こうした無駄を一掃し、会議を“レベルアップ”させるコツを説いた5冊の書籍を選り抜きました。
非効率な会議の生産性を上げ、きちんと問題解決できる場に変える。いずれも、そんなアイデ
この数字は、近年のアメリカにおける“会議”について出された試算です。
膨大なコストをかけているにもかかわらず、それに見合った成果を上げられる会議はそう多くありません。
同様のことは、日本においても言えるでしょう。
回数が多い、時間が長い、参加者が多い…。
今回は、こうした無駄を一掃し、会議を“レベルアップ”させるコツを説いた5冊の書籍を選り抜きました。
非効率な会議の生産性を上げ、きちんと問題解決できる場に変える。いずれも、そんなアイデ