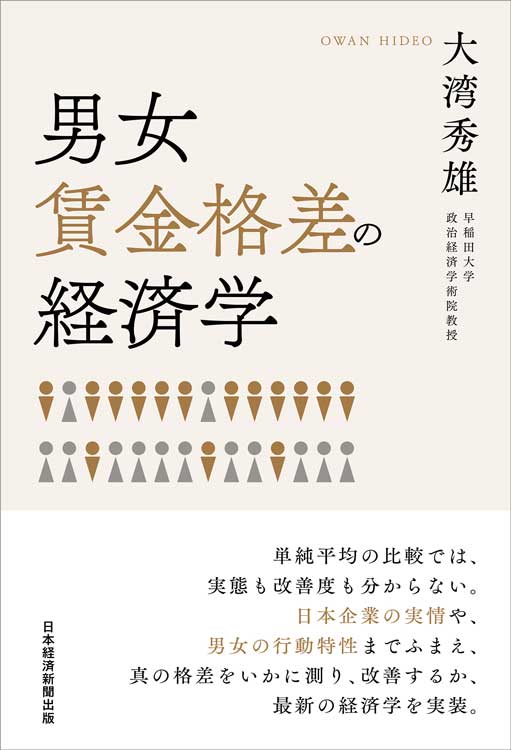2025年10月号掲載
男女賃金格差の経済学
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年6月25日
- 定価2,200円
- ページ数241ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
日本の男女賃金格差は22%と、欧米のどの国よりも大きい。だが、その解消に向けた企業の動きは鈍い。「日本の取り組みは周回遅れ」。こう指摘する人事経済学の第一人者が、原因と対策をわかりやすく説く。労働時間やジェンダーバイアスなど、格差を生む要因、企業が行うべき取り組み、さらには格差縮小に伴うメリットが示される。
要約
男女賃金格差を生み出す社会的構造
ここ数年、日本の男女賃金格差が話題に上ることが増えたのではないだろうか。
OECD(経済協力開発機構)の比較だと、2023年の日本のフルタイム労働者の男女賃金差は22%で、欧米のどの国よりも男女賃金差は大きい。
では、何が男女格差を生み出しているのか?
なぜ男女格差は生じるのか
私たちは男女賃金格差の原因を企業側に求めがちだが、そもそもは家庭内分業に起因している。
便利な家電が無かった時代、料理も掃除も洗濯も時間がかかった。そのため、男性が市場労働に専従し、女性が家事育児に専念することが、夫婦の生涯所得を最大化する上で最適だった。
多くの家庭が取る選択は社会規範となり、人々の期待を支配する。その結果、女性はどんなに優秀でも結婚や出産を契機に仕事を辞めるという期待が形成され、女性の育成にリソースをかけることは無駄な投資とされた。そのため労働市場において女性が差別されるようになった。
しかし技術の進歩により、昔なら毎日10時間かかった家事が今は2~3時間で済む。また、人材不足で、女性を活用しないと経済成長を確保できない状況も生まれつつある。こうした中、家庭内分業の非効率性が際立ってきたのが現代なのだ。
長時間労働のリターンと男女賃金格差
では、男女公平に扱う社会へとすぐに変えていけるかというと、簡単には変えられない。
その理由の1つに「労働時間」の問題がある。
ハーバード大学のクラウディア・ゴールディン教授らの研究によれば、経営職、コンサルタント、弁護士といった高収入の職業では、長い時間働くほど、単位時間あたりの賃金が高くなる。その上乗せ賃金は「長時間労働プレミアム」と呼ばれる。
男性はこうした長時間労働プレミアムを付与する職業(強欲ジョブ)を選んで高収入を得る。